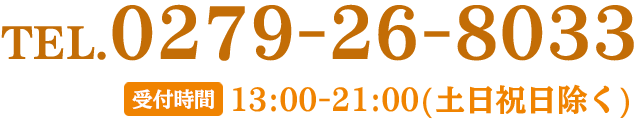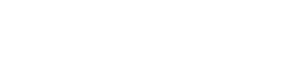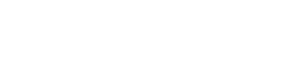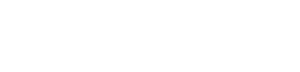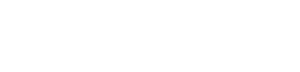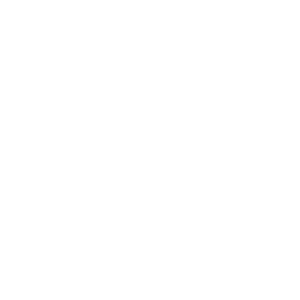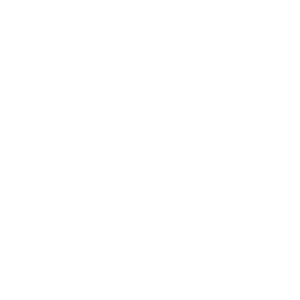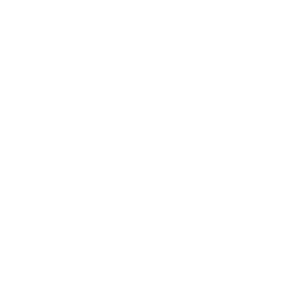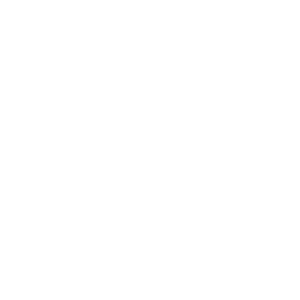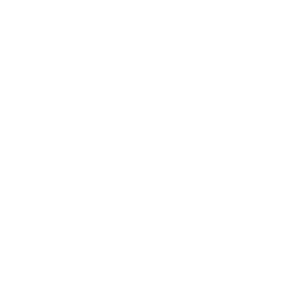デジタル全盛時代に「手を動かす学び」の価値を見直す/塾長ブログ
デジタル全盛時代に「手を動かす学び」の価値を見直す
近隣小中学校に通学のお子様をお持ちの保護者様へ(渋川・吉岡・榛東)
皆さんこんにちは。
うえだ未来塾の上田です。
今回は、私がいつも学ばせていただいている他塾の塾長さんがメルマガで取り上げていた「教育のデジタル化とアナログ学習の価値」について、共感する内容が多かったため、要点を抜粋してご紹介させていただきます。
教育のデジタル化とその課題
-
教育のデジタル化は一般化
学校でも家庭でもAI教材やオンライン学習が主流となり、効率的な学びが可能になりました。 -
ただし弱点も…
「分かったつもり」になりやすく、理解や記憶が浅くなる傾向も指摘されています。 -
手書き学習の効果
手を動かしてノートを書くと、キーボード入力よりも広範囲の脳が活性化し、記憶に残りやすいことが脳科学の研究でも明らかになっています。 -
身体性の重要性
図形を切ったり、地図に書き込んだりする“体を使った学び”が、抽象的な理解を助けると教育心理学でも裏付けられています。 -
あえて非効率を選ぶ意味
「効率的な学び」が重視される今だからこそ、手間のかかる学びが深い理解を生むこともあるのです。
当塾での実践と気づき
実は当塾も、開校当初はAIデジタル教材を導入していました。私一人で指導していることもあり、「自学自習で進められる教材」は非常に魅力的に映りました。
しかし、実際に使ってみる中で、いくつかの問題に直面しました。
-
人の関わりが必要な生徒が多い
説明動画が長くて集中できない、途中で眠くなってしまう、理解しているようで実はできていない…というケースが頻発しました。 -
学習の「型」が崩れてしまう
数学ではノートを使わずに暗算で解こうとしてミスが増えたり、英語ではタイピングには慣れても記述式になると書けないなど、「紙で書く」訓練が不足するという弊害がありました。 -
入試対策には不向き
学校の予習復習には良くても、応用力や記述力が求められる入試対策には人の指導が不可欠であると実感しました。
今、私が選んでいる方法
こうした経験を経て、今では「速読解力講座」を除き、基本的には紙と鉛筆でのアナログ指導を行っています。もちろん、デジタル教材を否定しているわけではありません。ただ、「何が子どもにとって最もよいか」を考えたとき、今のところ私は“手を動かす学び”が最も効果的だと感じています。
最後に
学びに「これが絶対に正解」という答えはありません。ただ、デジタル全盛の今だからこそ、あえて手間をかけるアナログの価値が見直されるべき時代なのかもしれません。
保護者の皆様にも、この視点を少しでもお伝えできたら嬉しく思います。
[2025-07-02]