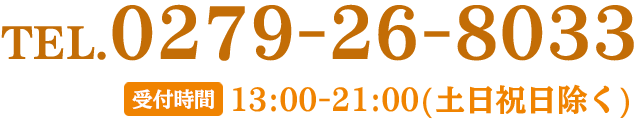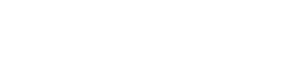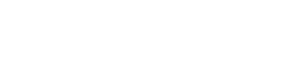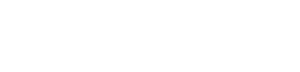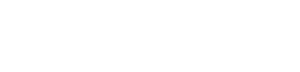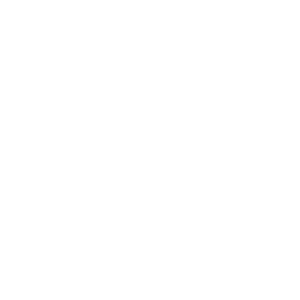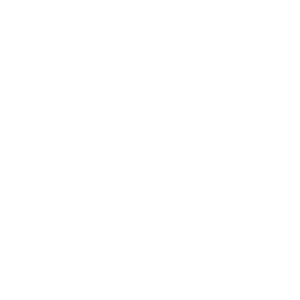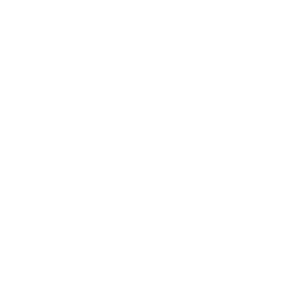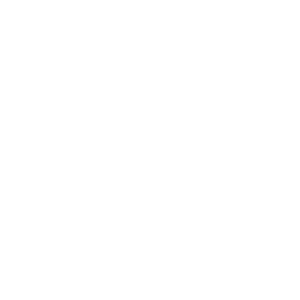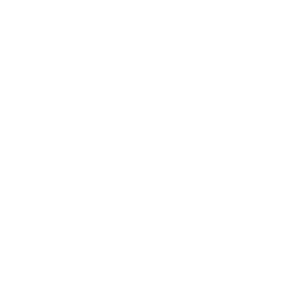得意な生徒への指導――先取学習の意味と成果/塾長ブログ
近隣小中学校に通学のお子様をお持ちの保護者様へ(渋川・吉岡・榛東)
皆さんこんにちは。
うえだ未来塾の上田です。
先日のブログで「中学2年生に中学3年生の統一テスト英語を解かせてみた話」を書きましたが、実はその続きがあります。今回は数学についてです。
トップ層の生徒に挑戦してもらった「統一テスト数学」
解いてもらったのは、学校の成績が常にトップにある生徒です。彼は学習の進め方が他の生徒と大きく異なります。英語・数学ともに“復習”ではなく“先取”を中心に学習し、夏期講習でも徹底して先へ進めました。
結果、英語は中2の内容をすでに全て終え、数学も2学期期末テストの範囲まで到達しています。
そんな彼に、中3統一テストの数学(一次関数や図形の応用問題)を解いてもらいました。一次関数は中2範囲、図形は中1範囲ですが、どちらも応用的に問われる良問です。
結果は、一次関数についてはほぼ満点レベル。図形は多少サポートをしましたが、理解の筋道は自分でつかんでいました。時間を計測していなかったので本番形式でどうかはわかりませんが、十分「力が定着している」と言える出来でした。
因みにこの「図形」の問題は3問全てが正答率10%未満でした。
先取は本当に意味があるのか?
正直に言えば、私自身も「ここまで先に進めて本当に身についているのか?」という疑問を持っていました。知識が“わかったつもり”で終わる危険は常につきまといます。
ですが、今回のテストで証明されたのは、「正しく指導された先取学習は、確かに力になる」ということです。特に一次関数のように学びたての単元を、応用問題まで解ける段階にまで自力で消化できていたのは、大きな成果でした。
得意な生徒にも戦略が必要
これまでのブログでは「数学が苦手な生徒をどう支えるか」について書きました。今回はその逆、得意な生徒にどう指導するかについてです。
英語でも同じです。例えば小学生から英語を習っている生徒や、すでに英検3級以上を持っている生徒。こうした“得意層”には、通常のカリキュラムだけでは物足りません。かといって本人の意思に任せれば「自分ができることだけを繰り返す」傾向も出てしまいます。
だからこそ、塾として“適切なレール”を用意し、その上を走らせることが必要なのです。得意な子にはさらなる挑戦を、苦手な子には確実な基礎固めを。それぞれに合わせた進め方を考えることで、全員が成長できます。
最後に
勉強が得意な生徒にも苦手な生徒にも、それぞれに合ったやり方があります。「全員に同じことをやらせる」では伸びないし、「本人の意思に任せる」だけでは偏りが出ます。
だからこそ塾は、生徒一人ひとりを見て、その子にとって最適なレールを敷くことが大切だと改めて感じています。これからも、どんなタイプの生徒にも対応できるよう試行錯誤を重ね、点数アップと成長を全力でサポートしていきます。
[2025-08-28]