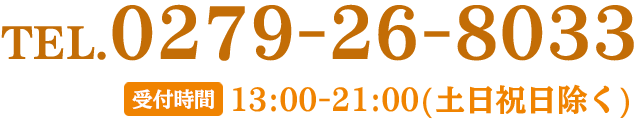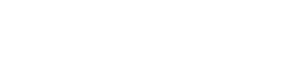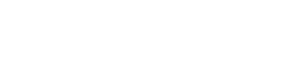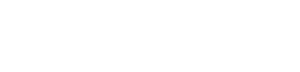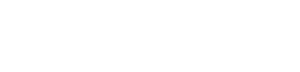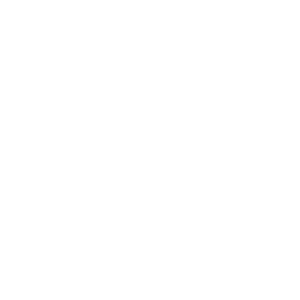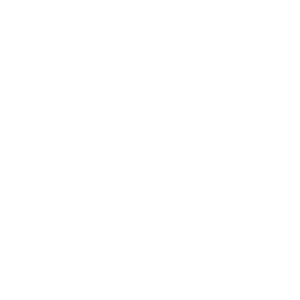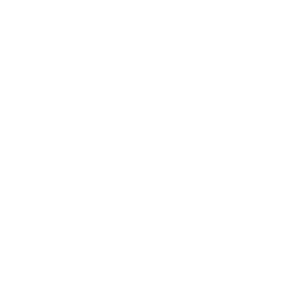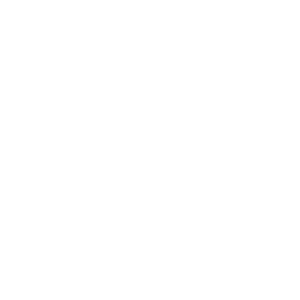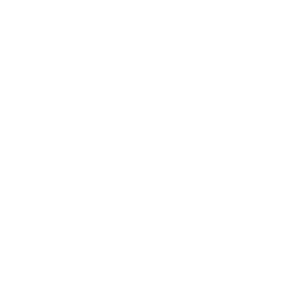数学が苦手なお子様への支援 ― テキスト選びと繰り返し方の工夫/塾長ブログ
近隣小中学校に通学のお子様をお持ちの保護者様へ(渋川・吉岡・榛東)
皆さんこんにちは。
うえだ未来塾の上田です。
前回のブログで「昨日できたのに今日はできない」というケースについて触れました。
これは単なるサボりではなく、手順を記憶に留める力(ワーキングメモリー) に関わっていることがあります。
そのような場合には「手順をカード化」することを紹介しました。
分配法則を例にすると、
-
Aと()の間には「×」が省略されている
-
×を入れて「A×(B+C)」と書く
-
AをBとCに掛けて「AB+AC」とする
といったように、ステップを整理し、勉強の最初に毎回声に出して説明させる。
同じ問題を繰り返すことが、「忘れる」ことへの対策になるというお話でした。
更に深掘りすると…
私は、数学が極端に苦手な生徒には「同じタイプの問題を大量に解かせる」ことはあまりしないようにしています。
しかし、以前はそれが良いものだと思って、やらせた時期もありましたが、今はその逆の方が良いのではないかという結論に達しました。
理由は簡単で、苦手な子ほど「繰り返す中で混乱し、途中で嫌になってしまう」からです。
むしろ大切なのは、少ない問題数を何度も繰り返し解くことです。
テキスト選びの工夫
ここで大切なのが「どんな教材を使うか」です。
塾用のテキストや学校のワークは、説明が短く、端的すぎることがあります。
数学が得意な子ならそれで十分ですが、苦手な子にとっては「どうしてそうなるのか」が分からず、自力で理解するのは難しいのです。(私もできる限り嚙み砕いて何度も何度も説明しますが・・・)
そこで私がよく使うのが、市販の「超基礎向け」の教材です。
特におすすめなのは 学研の『一つ一つわかりやすく』シリーズ。
全教科・全学年に対応していて、見やすく、解説も丁寧ですので、苦手な子でも取り組みやすい作りになっています。
「一人だけ違う教材」問題
もちろん、クラスの中で「自分だけ違う教材を使う」のが嫌だという子もいます。
そういう時は、保護者様に事情を説明し、「できるようになるための工夫」であることを理解していただくようにしています。
購入も保護者様にお願いすることが多いですが、その分「お子様に合った教材で確実に力をつける」効果が見込めます。
少ない問題数を繰り返す
苦手な子には、問題数が少なく、ページ数も抑えられた問題集が良いです。
少ない問題を「何度も繰り返し」やり切る経験が、自信につながります。
「たくさんやったけど結局覚えられなかった」よりも、「少ないけど全部できるようになった」という感覚の方が、次のステップにつながります。
私はこれまで、勉強が苦手な生徒を多く見てきました。
今でもそのような子たちが通っています。
一人一人の状況に応じて教材や方法を変えながら、できるようにしてあげること。
それが私のモットーです。
ぜひ一緒に、お子様の学力アップを実現していきましょう。
[2025-08-26]